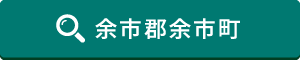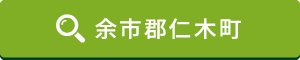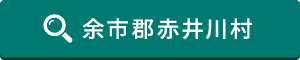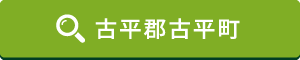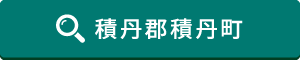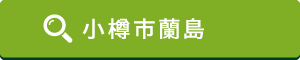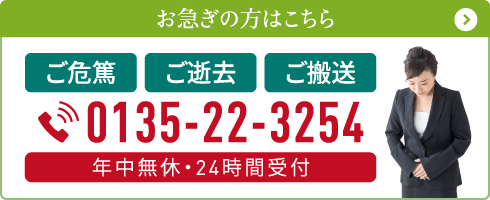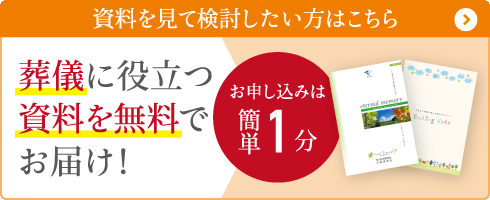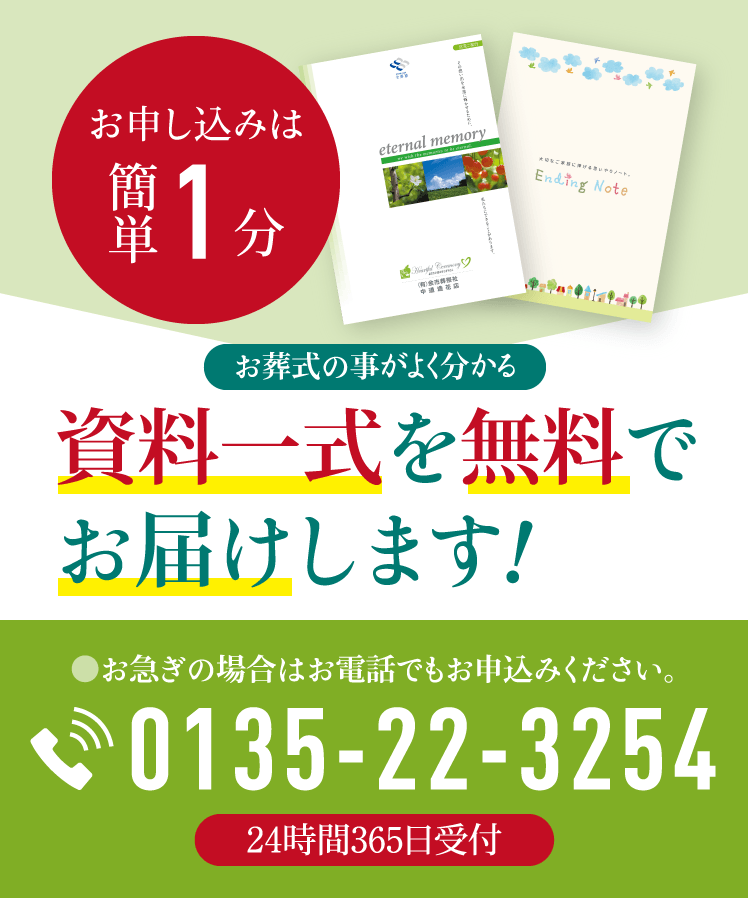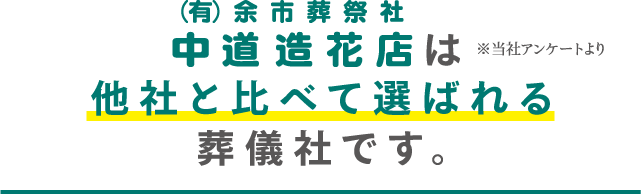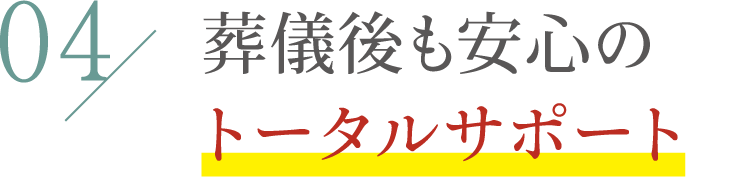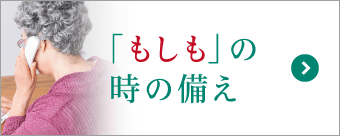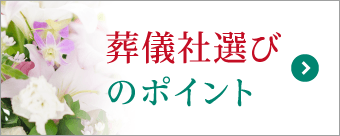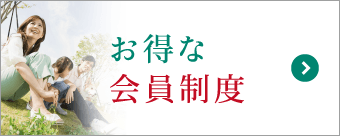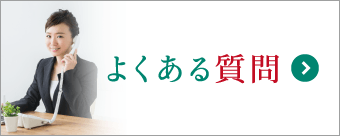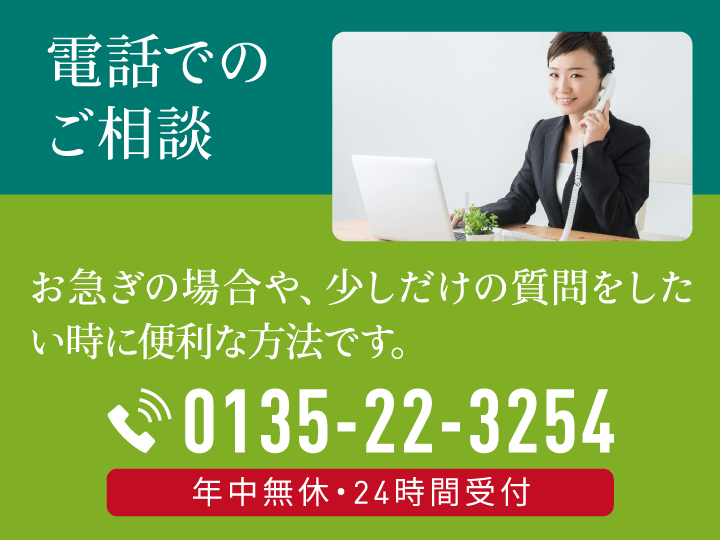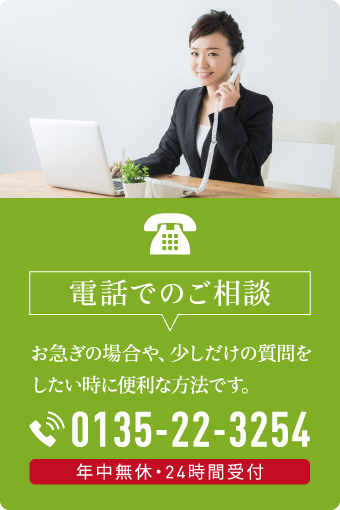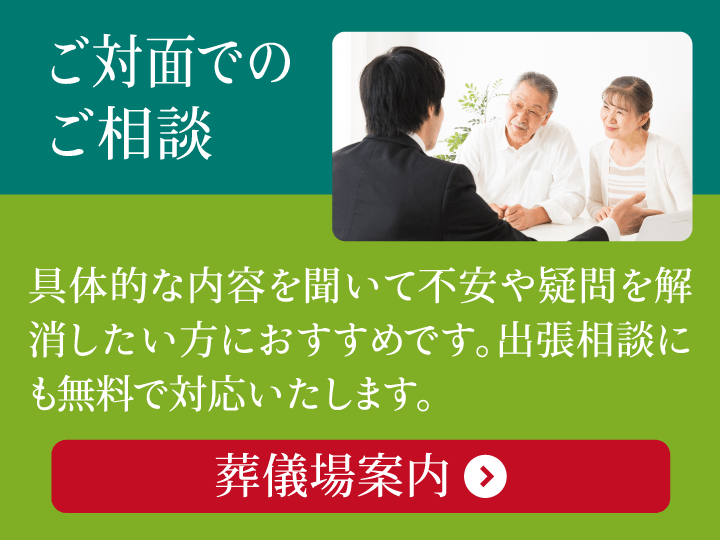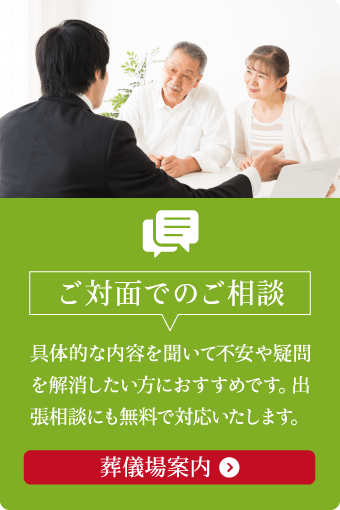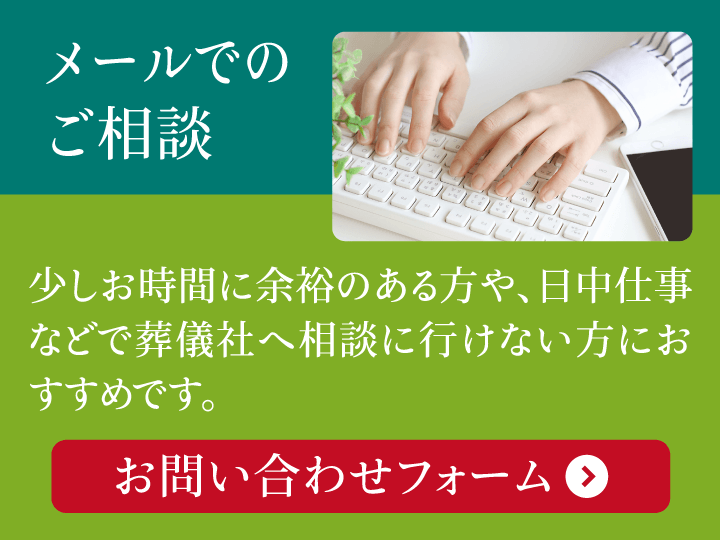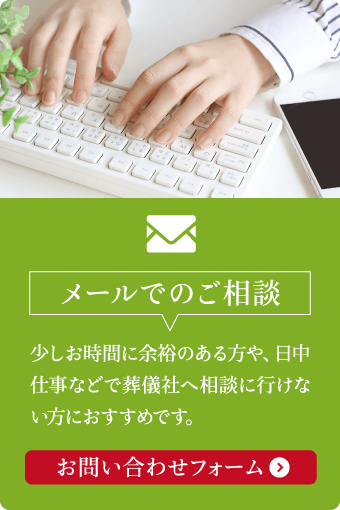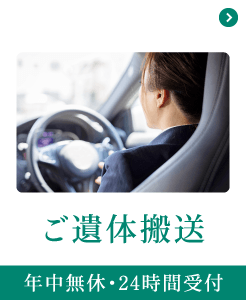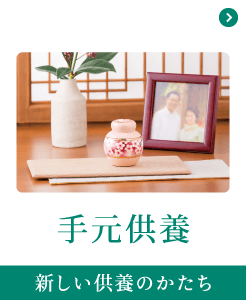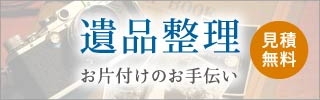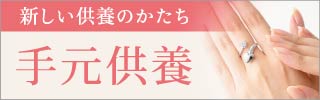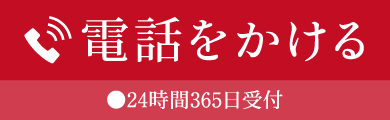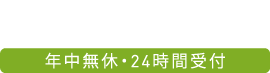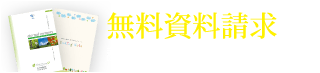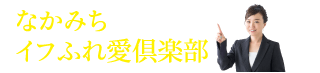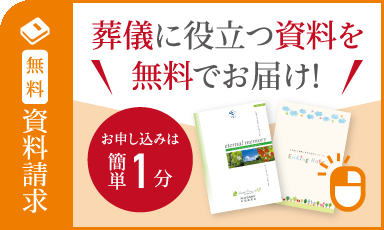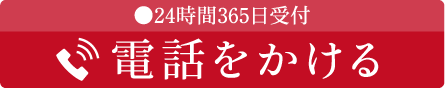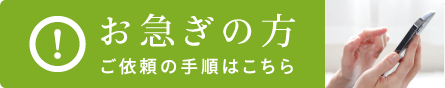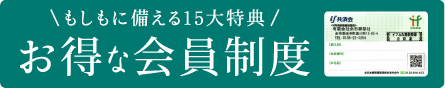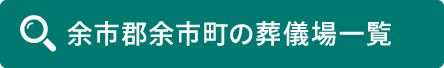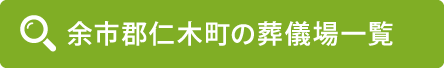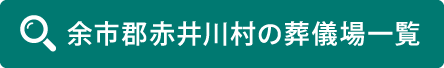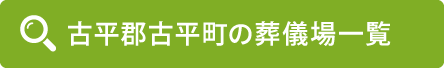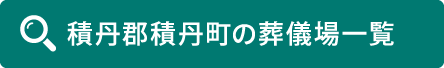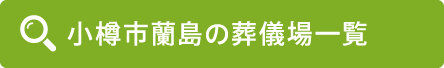春のお彼岸に向けて─供養の意味と地域の風習

1. お彼岸とは何か?─仏教行事としての意味
「お彼岸」とは、春分・秋分を中日とした7日間に行われる仏教行事です。春は3月、秋は9月にあり、いずれもご先祖様を供養する大切な期間として知られています。仏教の教えでは、私たちが生きるこの世(此岸)から、悟りの世界(彼岸)へ至るための修行の期間とされており、家庭では主にお墓参りや仏壇の清掃、法要などが行われます。春分は「昼と夜の長さが同じ日」であり、自然の節目でもあります。季節の変わり目に、家族でご先祖様のことを思い出し、感謝の気持ちを伝える文化が、今も多くのご家庭に受け継がれています。
2. 北国・余市町でのお彼岸─地域ならではの供養風景
余市町をはじめとする北後志地域では、3月もまだ雪が残る季節。それでも春のお彼岸が近づくと、地域の人々は少しずつ雪解けを感じながらご先祖様のお墓を訪れる準備を始めます。道路状況や墓地の除雪具合によっては、お墓参りが難しい場合もありますが、そのようなときでも仏壇に手を合わせたり、故人の好物を供えるなど、できる範囲で“気持ちを届ける”供養が大切にされています。余市町では、お彼岸のタイミングで仏壇周りを掃除したり、おはぎを作って供えるご家庭も多く見られます。形式よりも「想いを込めること」が重視されており、寒さの残るこの時期だからこそ、心温まる供養の時間となっているのが特徴です。
3. お彼岸に行いたい供養のかたち
春のお彼岸に向けて、できることを無理なく行うことが供養の基本です。たとえば以下のような行動は、いずれも「ご先祖様に気持ちを伝える」立派な供養のかたちといえます。
●仏壇の掃除とお供え(季節の花・おはぎなど)
●ご家族での墓参(可能であれば)
●故人の思い出を語り合うひととき
●法要の依頼やお寺へのお参り
最近では、外出が難しい方に向けてオンライン法要を取り入れる寺院もあります。地域の事情に合わせて、今の生活の中でできる供養を選ぶことが、家族や故人にとっても自然な姿です。
4. お彼岸をきっかけに、供養や終活を見直す
お彼岸のタイミングは、供養について見直す良い機会でもあります。たとえば「今後どのようにお墓を守っていくか」「将来的な供養の方法はどうするか」といったことを、家族で話し合ってみるきっかけになる方も増えています。また、仏壇やお墓の維持、納骨のタイミングなども含めて、事前に相談しておくと、将来の不安も軽減されます。余市葬祭社では、地域に根差した供養の相談や法要の手配も承っています。春のお彼岸を通じて、今後の備えについても考えてみてはいかがでしょうか。
5. 想いを伝える、静かな祈りの時間を大切に
春の訪れを感じるお彼岸の時期。少しずつ暖かくなる空気の中、静かに手を合わせる時間は、ご先祖様との心のつながりを感じられる大切な瞬間です。たとえお墓参りに行けなくても、供養の形に正解はありません。気持ちを込めて仏壇に花を供えたり、故人の好きだった話を家族で語り合ったりすることが、何よりの供養になります。余市町で受け継がれてきた「想いを大切にする文化」を、春のお彼岸にも感じていただければと思います。
タグ:お彼岸, 供養の意味, 墓参り, 仏壇, 春の行事, 余市町, 北後志, 家族の供養, 余市葬祭社, 法要相談
投稿者プロフィール

- 余市葬祭社「中道造花店」は、長きにわたり葬祭サービスを通じて、北後志の皆様と共に歩んでまいりました。遺されたご遺族様、ご親族様に心から満足していただけるご葬儀が行えるように、真心を込めてお手伝いさせていただいております。これからも地域密着型の葬儀社として「送る人」「送られる人」の想いに寄り添い、充実した葬送サービスをご提供してまいります。
最新の投稿
 葬儀の準備2026/01/22もしもの時、最初に動くのは誰?――冬の緊急時にも慌てない連絡・判断の整理方法
葬儀の準備2026/01/22もしもの時、最初に動くのは誰?――冬の緊急時にも慌てない連絡・判断の整理方法 葬儀の準備2026/01/08葬儀内容はいつ・どう決まっていく?――打ち合わせで確認される流れと考え方
葬儀の準備2026/01/08葬儀内容はいつ・どう決まっていく?――打ち合わせで確認される流れと考え方 その他2025/12/22余市町での家族葬の実際─地域に合わせた葬儀の工夫
その他2025/12/22余市町での家族葬の実際─地域に合わせた葬儀の工夫 葬儀後の知識2025/12/03思い出を整理する時間─遺品整理と心の向き合い方
葬儀後の知識2025/12/03思い出を整理する時間─遺品整理と心の向き合い方